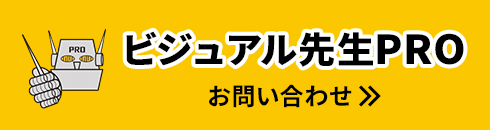品質管理とは? 3つの構成要素や基本的方法を解説
顧客満足度の高い製品やサービスを提供するには、品質管理の実施が必要です。
品質管理は製品やサービスの品質を保つための取り組みであり、顧客からの信頼を獲得するために欠かせません。また高品質を維持するには、品質管理の内容は定期的に見直す必要があります。
本記事では、品質管理の基本的な方法や重要な概念について解説します。
品質管理とは
品質管理は、製品やサービスの品質を一定水準に保つために欠かせない取り組みです。人の命に関わる医療分野や食品分野では、特に厳重な品質管理が求められます。
英語では品質管理のことを「Quality Control」と言い、QCと略して呼ぶ場合もあります。
従来の品質管理では、人の目で製品やサービスのチェックを実施していました。近年は品質管理でもデジタル化が進んでおり、システムを活用した高精度な管理が可能です。
また、データに基づいた品質管理を実施することで、生産性や顧客満足度の向上を実現できます。
品質保証との違い
品質管理と混同しやすい言葉に「品質保証」があります。
品質保証は、製品やサービスが顧客の要望を満たしていることを確認するための取り組みです。品質管理とは異なり、完成した製品を手にした顧客がどのように感じているかを重視します。
品質を保証するための取り組みは、顧客の声の収集やデータ分析、フィードバックなど多岐に渡るのが特徴です。
より良い製品やサービスを顧客に届けるには、品質管理だけでなく品質保証も欠かせません。
品質管理に関する規格と資格
品質管理に関する規格に「ISO9001」があり、「同じ品質やレベルで製品やサービスを提供できること」を意味しています。全世界で100万を超える組織が取得しており、円滑な取引のために必要な指標です。
また、品質管理に関する資格には以下があります。
● 品質管理検定(QC検定)
● 信頼性技術者資格認定制度(JCRE)
● R-Map実践技術者認定制度
ISO規格や資格の取得によって品質担保につながるので、取得しておくのが良いでしょう。
品質管理が必要な3つの理由
品質管理は、製品の品質低下や不良品の販売を防ぐために必須です。ここでは、品質管理が必要な3つの理由を解説します。
● 顧客満足度の向上
● 製品やブランド価値の向上
● コストの削減
1. 顧客満足度の向上
一定以上の水準が保たれた製品やサービスを提供することは、顧客満足度の向上につながります。
顧客が品質に納得していれば、継続的に購入してくれる可能性もあるでしょう。口コミや評判が拡散されることで、売上や利益の向上が実現できます。
ただし、顧客は基本的に信頼できるか分からない企業の製品は購入しません。類似商品であれば、名の知れた他社製品を選んで購入するのが一般的です。
そのため、品質管理を実施して顧客満足度を向上させる必要があります。
2. 製品やブランド価値の向上
企業が自社の製品を販売して利益を上げるには、製品やブランドの価値向上が欠かせません。品質の高い製品・サービスを提供し続けることは、製品やブランドの価値を自ずと向上させます。
例えば、従来の中国製品は質が低く、多少価格が高くても日本製を選ぶ方がほとんどでした。しかし、近年は質が向上したことで、安価な中国製品を選ぶ方も増えています。
このように、顧客が自ら選んでくれる製品を提供するためにも、品質管理は重要です。
3. コストの削減
品質管理を実施するにはコストがかかりますが、長期的に見るとコストの削減が可能です。
品質管理が徹底されていない製造現場では、不良品が発生します。不良品が多ければ多いほどロスにつながるため、現場には不良品を防ぐ対策が必要です。
品質管理を実施していれば、不良品の発生を未然に防げるのでロスが減らせます。
また、品質管理の過程で製造プロセスが最適化されるため、生産性が高まり製造コストの削減にもつながるでしょう。
品質管理を構成する3つの要素

品質管理の業務は以下の3要素で構成されています。品質が保証された製品やサービスを顧客に提供するには、3要素の全てが欠かせません。
ここでは、品質管理の業務内容について詳しく解説します。
● 工程管理
● 品質検証
● 品質改善
1. 工程管理
工程管理は、期日までに不良品を出さずに決められた数を製造するための取り組みです。具体的には製造に必要な人材や材料、設備などを管理します。
工程管理の目的は一定水準以上の品質を保った上で、業務プロセスの無駄を減らし、生産性を高めることです。また、材料費や人件費などのコスト削減も目的に含まれています。
具体的な方法は、作業手順の標準化や人材育成などです。作業内容をマニュアルに落とし込み、誰が担当しても同じ品質で製造できるようにします。
また、マニュアル通りの作業が行えるように人材育成を実施することで、効率的な製造体制の構築が可能です。
2. 品質検証
品質検証では、製品を製造するために仕入れた原材料や部品などの状態を検査・管理します。
製造プロセスが適切であっても、原材料や部品に不備があれば、不良品の発生は避けられません。一定水準以上の製品を製造するためには、品質検証が必要です。
また、品質検証では検査・検品を実施するだけでなく、原材料や部品、完成した製品に規格を設定します。これらに欠陥がないかを確認すると同時に、合格ラインを超えているかを検品するのが特徴です。
他には、設定した規格や合格ラインが、客観的に見て問題がないかを確認するための審査も実施されます。
3. 品質改善
品質改善では製造過程で欠陥品が生じる原因を特定し、問題を解消することで製品そのものの品質を改善します。
工程管理や品質検証の実施だけでは、欠陥品の発生を完全には防げません。また、欠陥品とまではいかなくとも、品質基準に満たない製品が製造されるケースもあります。
欠陥品や不適合品が発生した場合には原因を特定して、再発を防がなければなりません。
品質改善では現場での聞き取りや仮説検証を実施し、問題点を徹底的に洗い出します。原因を特定・分析した後は、同じ問題が発生しないように対策を立てることが重要です。
品質管理に用いる3種類の方法
品質管理には多様な方法があり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、品質管理に用いる方法の中から、特に押さえておきたい3種類を解説します。
● PDCAサイクル
● QC7つ道具
● インダストリアルエンジニアリング(IE)
1. PDCAサイクル
PDCAサイクルとは、目標達成や業務改善を実施する際に活用されるフレームワークです。PDCAは以下4つの頭文字を表しています。
● Plan(計画)
● Do(実行)
● Check(評価)
● Action(対策・改善)
PDCAサイクルは、1950年代に品質管理の父と呼ばれるアメリカの統計学者ウィリアム・エドワード・デミングによって提唱されました。
元々は品質管理のフレームワークですが、現在では経営管理や人材マネジメントなど、多様なシーンで活用されています。
Plan→Do→Check→Actionのステップを順番に実施し、Actionが終わったらまた最初のPlanに戻るのが特徴です。
各ステップで行う具体的な方法を紹介します。
Plan(計画)
Plan(計画)では、問題解決や品質を維持するための目標を設定し、それを達成するための具体的な行動計画を作成します。
PDCAサイクルの中でも特に重要なステップであり、具体的な計画を立てることが必要です。現状を正確に把握して、具体的な数値目標の設定により後に評価しやすくなります。
最初の計画段階で明確な目標が設定されていれば、後のステップで迷うことなく行動に移せるでしょう。
Do(実行)
事前に立てた計画に従って、実際に行動を起こします。実行した内容を後で客観的に振り返るために、行動プロセスを詳細に記録しておきましょう。
具体的には、実行中に起きたことや進捗状況まで細かく記録してください。
また、計画した通りに進まない場合には、問題点を記録することが重要です。些細なことでも記録に残しておけば、後で評価する際に役立ちます。
Check(評価)
事前に立てた計画通りに行動した結果を評価する段階です。評価する際は単に「できた」「できなかった」だけでなく、なぜその結果になったのかを分析してください。
目標を達成できた場合は、達成できた要因を分析しましょう。評価する際には具体的な数字や統計データを参照することで、新しい課題が見つかる場合があります。
Action(対策・改善)
評価の段階で分析した結果を基に、今後の改善案を考えます。目標を達成できた理由の検討に、有益なヒントが含まれている場合があります。
また、改善案は今後試してみるべき行動や、行わない行動に分けて考えることが大切です。再びPlanに戻ることを考慮して、改善案に優先順位を付けましょう。
2. QC7つ道具
QC7つ道具は、品質管理(QC)を実施する際に活用される7種類の方法の総称です。データに基づいた客観的な分析によって、問題の本質を見抜きます。
QC7つ道具は1960年代の日本で誕生し、統計的な方法を取り入れているのが特徴です。日本科学技術連盟(JUSE)の専門家チームが中心となってQC7つ道具を普及したことで、現在でも品質管理の基本的な方法として活用されています。
品質管理に活用される7種類の方法は以下の通りです。
● パレート図
● 特性要因図
● グラフ
● ヒストグラム
● 散布図
● 管理図
● チェックシート
パレート図
パレート図は項目ごとに数量の大きい順に並べた棒グラフと、各項目の累積構成比を表す折れ線グラフで構成されています。
全項目のうち大きな比率を占めるものがどれかを明確にできるのが特徴です。結果に対して影響が大きい要因に集中して対処したい場合に役立ちます。
特性要因図
特性要因図はある問題点の要因について書き出し、どの要因が特性の変化に大きく影響するかを可視化した図です。図の見た目が魚の骨に似ているため、フィッシュボーンチャートと呼ぶ場合もあります。
問題点を書き出す際は、ブレーン・ストーミングを活用するのが効果的です。
グラフ
グラフは2つ以上のデータの関係性を視覚的に表現しており、数値の比較や変化を把握しやすいのが特徴です。品質管理においては以下の5種類がよく利用されています。
● 棒グラフ
● 折れ線グラフ
● 円グラフ
● 帯グラフ
● レーダーチャート
ヒストグラム
ヒストグラムはデータが存在する範囲を一定ごとに区切り、それぞれの度数を表にまとめて棒グラフで表したものです。一般的に横軸にはデータが存在する範囲、縦軸には範囲ごとの数量を記載します。
グラフの形状を見ることで、工程上の問題点を推定する際に役立ちます。
散布図
散布図は一つの事象に関する2項目のデータをX軸・Y軸に取り、データを点の集合で表します。2つの項目にどのような相関関係があるかを把握でき、問題改善の糸口を見つけられるのが特徴です。
管理図
管理図は、品質や工程などの管理状態を可視化して把握するために使われる図です。工程上の品質のばらつきが偶然発生したのか、異常によって発生したのかを判断する際に役立ちます。
目標値を中心線、その上下に上方管理限界線と下方管理限界線を配置し、取得データを折れ線グラフで表すのが特徴です。
チェックシート
チェックシートはあらかじめ設定した項目に沿って、データを記録するための用紙です。不具合を未然に防ぐために使用され、効率的なデータ収集と整理に役立ちます。
点検用と調査用の2種類があるので、目的に合わせて使い分けましょう。
3. トヨタから始まったインダストリアルエンジニアリング(IE)
インダストリアルエンジニアリング(IE)は、工程や作業内容の分析によって作業の無駄や属人化を排除するための方法です。トヨタの現場や工場で採用されており、トヨタ生産方式の基礎となった方法として知られています。
作業者はマニュアルに沿って作業を行うため、作業のバラつきがなくなり品質の安定化につながるのが特徴です。
また、作業者の動作を分析することで無駄な動作を見つけ出せるので、業務効率を向上させられます。さらに、製造工程の分析によってボトルネックを特定し、生産性を向上させられるのも特徴です。
品質管理の実施に必要な4M
適切な品質管理を実施するには4Mが必要です。4Mは以下要素の頭文字であり、高品質な製品を製造するには4Mへの理解が欠かせません。
ここでは、品質管理の実施に必要な4Mについて詳しく解説します。
● Man(人)
● Machine(機械)
● Material(材料)
● Method(方法)
1. Man(人)
Man(人)は製造業を支える要素であり、人なくして製造業は成り立ちません。
品質管理におけるManは、製造業の中でも特に現場で作業する人材を指しています。生産ラインの自動化が進んでも無人で製造を続けることはできず、何かしらの工程で必ず人が必要です。
製造現場では生産性の向上が課題となっていますが、システムによる効率化だけでなく、従業員の行動を変えることも重視されています。そのため、従業員に必要な技術を身に付けさせ、快適に働ける環境を提供することも品質管理の一環と言えるでしょう。
2. Machine(機械)
製造現場には多様な機械が導入されており、高品質な製品を製造するには欠かせない存在です。
機械の性能や状態は製品の品質だけでなく、業務の安全性にも影響を与えます。例えば、ベテランの従業員が機械を操作していても、メンテナンスが行われていなければ、不良品が発生するかもしれません。また、事故やけがにつながるリスクもあります。
他には、機械のレイアウトも品質の高い製品を製造するには重要です。適切なレイアウト設計ができていれば、業務効率の向上につながります。
3. Material(材料)
Material(材料)は、製品を製造する際に使われる原材料や資材のことです。
製造現場において材料は必要不可欠であり、適切な材料がそろっていなければ高品質な製品を製造できません。
材料は必要に応じて在庫として備蓄する必要があります。無駄な在庫を抱えると、コストの増加につながるので注意が必要です。
また、材料をどこから調達すべきかも、品質管理の際に考慮しなければならない要素です。無駄をなくすために、材料の把握と管理を徹底しましょう。
4. Method(方法)
品質管理において、Method(方法)は作業方法のことを指しています。
一定の品質を維持した製品を製造するには、適切な方法で生産ラインを動かさなければなりません。品質管理に必要な他の要素がそろっていても、適切な方法で作業が行われていなければ、不良品が発生する可能性があります。
また、正しい作業方法を守らないことで、事故が発生するリスクも高くなります。リスクを抑えるためにも、従業員に作業方法を示して遵守させるようにしましょう。
客観的にデータを分析して適切な品質管理を実施しよう
品質管理は、自社の製品が一定水準以上の品質を保っているかを確認する重要な業務です。製品やサービスの品質を高めて顧客満足度を向上させるには、品質管理の徹底が欠かせません。
品質管理には多様な方法があり、自社の状況に応じた方法を選択することが必須です。また、効率的に問題の原因を特定して対策を立てるためには、客観的にデータの分析を行いましょう。
成電社ではMethod(方法)に特化して効率化を図る作業マニュアル作成ソフトの「ビジュアル先生PRO」を取り扱っています。製造プロセスの作業の均一化、品質安定化にお役立ていただけますので、ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。